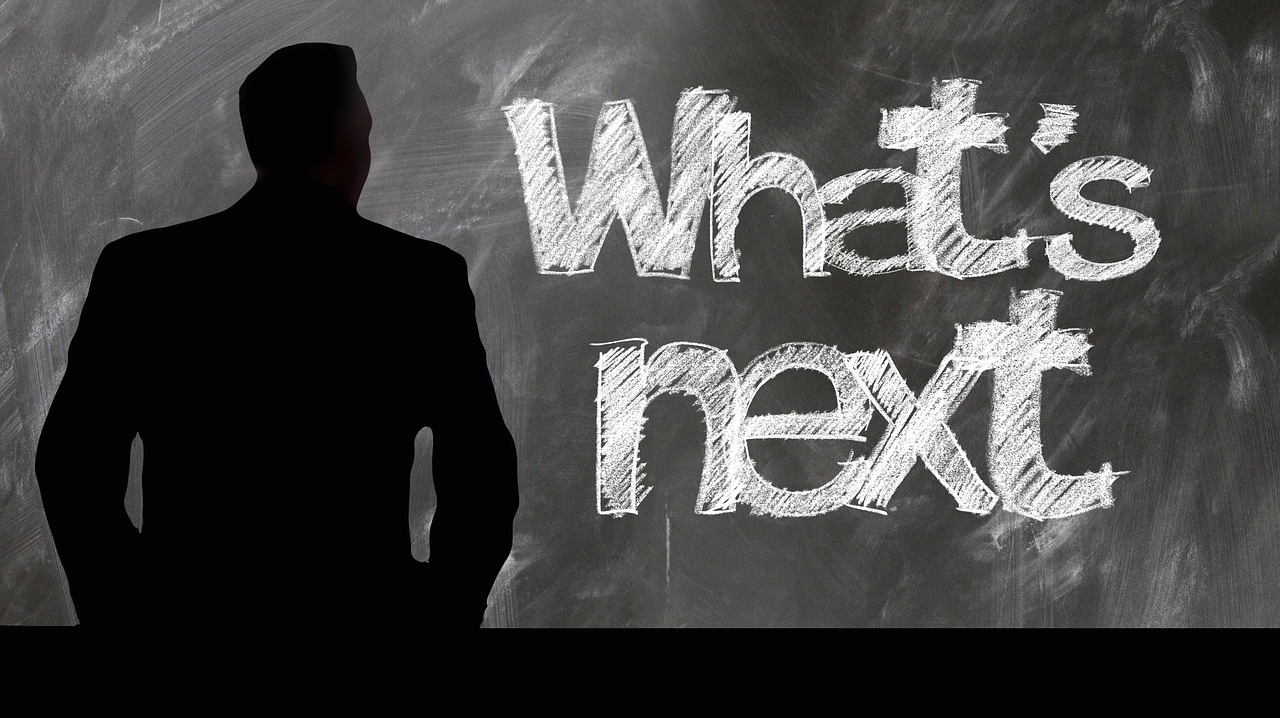
2019年4月1日に働き方改革関連法が
施行され、サラリーマンの副業・兼業が
本格的に解禁になりました。
今では副業をするのが当たり前に
なっていますね。
なぜこれほど副業が拡大しているのか。
その理由は「少子高齢化」です。
国立社会保障・人口問題研究所が発表した
「日本の将来推計人口」によると、
2015年時点で1億2700万人
2063年には9000万人を下回り、
さらに100年後の2115年には
5060万人まで激減すると予測。
2036年には3人に1人が65歳以上という
「超々高齢社会」が訪れようとしています。
「人口減少」と「高齢化」は
回避できません。
これは問題ではなく現実です。
また、厚生労働省は今月3日、
一人の女性が生涯に産む子供の数を示す
合計特殊出生率が2021年は
1.30になったと発表しました。
6年連続の低下で、
出生数も過去最少となっています。
人口を維持するためには
2.06~2.07が必要とされ、
1.5未満が超少子化、
1.3未満はさらに深刻な区分となり、
少子化対策が急務の現状です。
自身と日本社会の将来を考える上で、
“人口減少”と“高齢化”は、大前提です。
定年年齢も段階的に引き上げられており、
1980年代前半までは55歳が一般的でしたが、
1986年に高年齢者雇用安定法が
制定されると60歳定年が努力義務に。
2000年の改正法では
65歳定年が努力義務となり、
2012年改正法で完全に義務化。
政府は現在70歳定年を目指しています。
これまでの流れから考えると、
2020年代には実現するでしょう。
政府が定年を延長したがる理由は、
言うまでもなく公的年金の
受給開始年齢を引き上げるためです。
年金を含めた社会保障にかかる費用は、
2011年度は約108兆円だったのに対し、
2025年度は約150兆円まで
増大すると見られています
(厚生労働省、2012年推計)
政府は、もうすでに莫大な借金を
しているため、社会保障を国に
期待している場合ではありません。
現在の医療費の自己負担割合は
6〜70歳が3割、
70〜74歳が2割、
75歳以上が1割です。
しかし、国にお金がない以上、
高齢者優遇も限界があり、
高齢者医療費も上がるでしょう。
2019年10月に消費税が10%に
増税しました。
でも、まだまだ上がると思います。
仮に定年が延長されたとしても、
全員が健康で働き続けられるとは限りません。
これからは「自己責任の時代」です。
長く働ける(遊べる)ための
「健康知識」
老後、年金に頼らない
「資金計画」
が本当に大事です。
たった一回きりの人生、
他の誰でもない自分の人生、
今日も後悔のない1日を!!
自分の未来は今日決まる!
END















